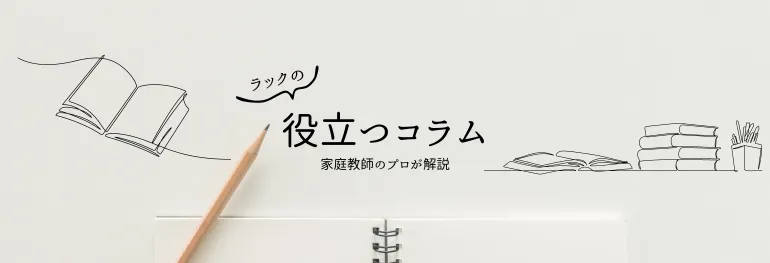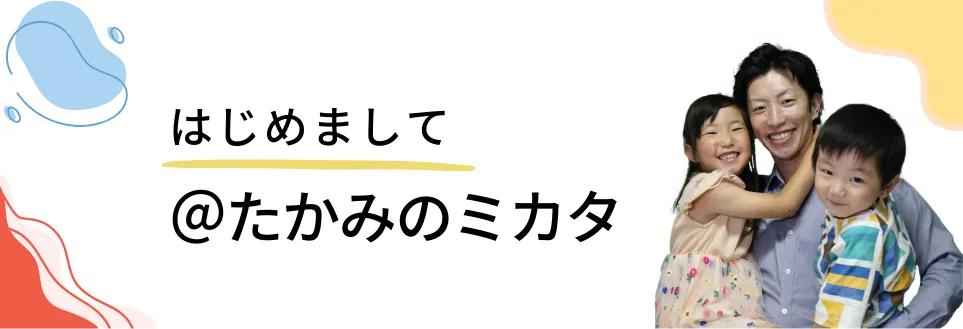受付時間 13:00〜21:00
志望校の選び方GoodLuck大作戦‼️

 たかみー
たかみーこんにちは、家庭教師のLUCKです!



急に寒くなってきましたが皆さんどうお過ごしでしょうか?
早いもので2025年も残り2ヶ月です🍂。
中学3年生はそろそろ本格的に志望校を決めなければいけない時期になりました。



「志望校はいつから決めればいいですか?」
保護者の方から最も多く頂くご相談のひとつです。



しかし実は、志望校の“決め方”や“考える深さ”は、学年によって大きく変わります。
中学3年生には「現実の合格可能性に向き合う覚悟」が求められますし、中学2年生には「方向性を固めるための情報収集」が重要になります。
中学1年生では、そもそも“名前で志望校を決める必要すらありません”。
つまり、



“今の学年”に合わせた適切なステップを踏めているかどうか
これが、志望校選びの成功を左右します。



今回は、今の時期(秋~冬)に保護者が意識すべき「学年別・志望校の考え方」 をわかりやすく整理してお伝えします。
【学年別】今の時期に志望校はどう決めるべき?中1・中2・中3で意識がまったく違います


中学3年生:現実を見据えて「志望校を確定する段階」
中学3年生は、すでに“志望校を考える”ではなく、
「最終的な受験校を決める時期」 に入っています。
特に重要なのは、次の2点です。
- 模試の結果だけで判断しない(内申・倍率・出題傾向も加味する)
- “合格できるか”だけでなく“3年間通えるか”までイメージする
親としては「がんばればいけるよ」と励ましたくなる時期ですが、過度な期待でプレッシャーをかけるのは逆効果。
適切なのは、“本人が最終的に納得して選べるように情報を整えてあげること”です。
中学2年生:志望校の“方向性”を固める準備期
中学2年生のこの時期は、「志望校の名前を決める段階」ではありません。
むしろ大切なのは、次のような“志望校のタイプ・方向性”を見定めることです。
- 自由な校風か、指導が厳しい進学校か
- 部活動中心か、大学進学実績を重視するか
- 共学か、男女別学か
- 公立を軸にするか、私立も含めて考えるか
これらの「軸」が固まってくると、
候補校の“数”ではなく“質”が絞られていきます。



特にこの時期に効果的なのが、以下の行動です。
- 秋の文化祭・学校見学で“雰囲気”を感じる(数字より空気感)
- 学校パンフレットだけでなく 在校生の声・SNSの情報も取り入れる
- 偏差値ではなく 「この生活に3年間ワクワクできるか」 を基準にする
さらに現実面では、内申点や定期テストの重要性がここから一気に上がります。
「まだ大丈夫」と油断してしまうか、「今から整えておくべき」と気づけるかで、翌年のスタートラインがまったく変わります。
中学1年生:まだ“決める必要はない”。将来の種まきをする時期
中1の場合、志望校という“名前”を決める必要はまったくありません。



それよりも重要なのは、次のような“世界観”に触れることです。
- 「どんな高校生活がしたいか」をイメージさせる
- 部活・制服・学校行事など “体験への憧れ”を育てる
- 兄姉や先輩・YouTubeなど“リアルな高校生の姿”を見せる
- 文系・理系・国際・芸術・スポーツ… ざっくりとした方向性だけ意識できれば十分
この時期で最大のポイントは、
「学力の伸びやすさは、学習習慣がついているかで9割決まる」という事実です。
- 定期テスト前だけ頑張る習慣ではなく
- 「ふだんから机に向かえる人間かどうか」



この基盤を作れた生徒だけが、中2・中3で一気に伸びていきます。
“志望校の名前”よりも“学習の土台”と“価値観への意識”を整える段階だとお考えください。
まとめ:志望校選びは「学年ごとに正しいステップを踏めているか」がすべて
多くの保護者の方が「うちは出遅れていないだろうか」と不安になりますが、
正しく学年ごとの課題を把握できていれば、スタートが遅すぎるということはありません。
- 中3
-
現実的な最終判断・合格可能性と生活の両面を見る
- 中2
-
方向性を固める“深い情報収集の年”
- 中1
-
世界観・学習習慣の“土台づくりの年”
志望校とは、“ただの偏差値選び”ではなく、
「お子さんが3年間、後悔なく通い続けられる場所を選ぶプロセス」です。
もし「うちの子の場合はどう考えれば?」というような 個別のご相談 があれば、
現在の成績状況・通えるエリア・性格面などを踏まえた 具体的なアドバイス もご提供可能です。



まずはお気軽に無料体験授業をご利用ください。